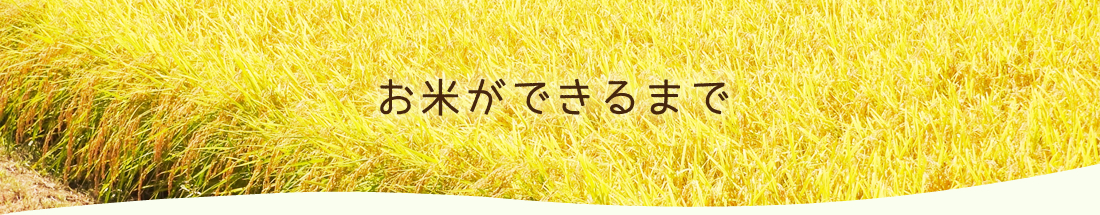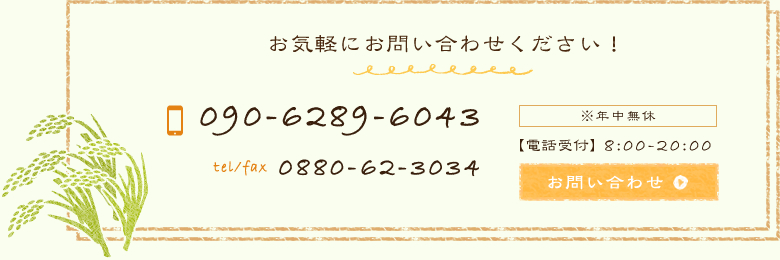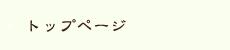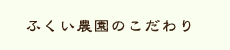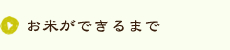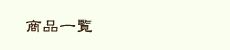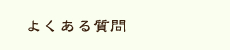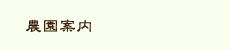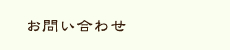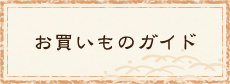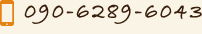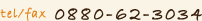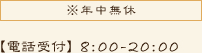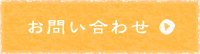- トップページ
- >
- お米ができるまで
お米ができるまでの流れ
お米作りは暖かくなり始めた春に苗作りから始まります。
前年のお米の中から選り分けた種籾を水に浸してたっぷりと水分を吸わせ、発芽しやすい状態にします。

田んぼに堆肥や肥料を与えてしっかりと耕します。
この作業は稲がすくすくと元気に育つために欠かせない重要な作業です。

天候などの気象条件を確認し条件のいい日に、水を張った田んぼに田植えをします。
田植え後の稲はまだまだ小さな赤ちゃんなので、何回も田んぼに足を運んで大切に育てます。

稲は夏の暖かい時期によく成長します。
この時に雑草などに栄養が取られないよう、こまめに草むしりをしたり、良い栄養を吸収して成長するように肥料を与えます。
また害虫の駆除のために農薬を最小限に抑えながら与えます。

田んぼが一面黄金色に変わり、稲穂が垂れてきたらいよいよ収穫です。
穂が出てきてから積算温度を考慮して最適な収穫時期に収穫をします。
穂の先にある籾は乾燥させて貯蔵し、来年の種籾にします。

米ぬか、鶏糞、ブロッコリー、籾殻などを使って来年のための土壌づくりをします。
来年も美味しいお米ができる良い土壌になるように今年の感謝と豊作の願いを込めて行います。
美味しい炊き方

- お米を計る
- カップ一杯のお米を計る時でも、多めに計る人と少なめに計る人がいらっしゃいます。
お米の計り方がバラバラでは、水の量をしっかり計っても意味がなくなってしまいます。お米はカップにすりきりで毎回同じ量になるようにしてください。

- お米を洗う
- 計量したお米は表面の糖や油を落とすためにさっと水で洗い流します。
お米は水に触れるとすぐに臭いを吸収してしまうので、あらかじめ容器に水を張っておき、一気に入れてさっとかき混ぜます。

- お米を研ぐ
- 美味しいお米のためには研ぐ作業が最も重要になります。
表皮の部分に当たるアリウロン層の残留物を取り除くためにお米同士をすり合わせます。
お米の研ぎ方は時期によって最適な方法・回数が変わります。 - 【新米】
指を立てて円を描くように軽く研ぎます。
11月~4月:3、4回研いですすぎ2回が目安です。
9月~10月:3、4回研いですすぎ1回が目安です。 - 【古米】
古米は匂いが残らないようにお米とお米をすり合わせて、ギュッと押すように研ぎます。
4月~8月:3、4回研いですすぎ2回が目安です。
8月~新米ができるまで:臭いが消えるまで研ぎます。

- 浸水させる
- お米を浸水させる時間は、新米は40分~1時間、古米は1時間を目安にしてください。
春~夏は冷たい水に浸水させると美味しくなります。

- 水切りをする
- お米に余分な水気があると水加減が正確にできなくなります。
しかし、ざるに上げて時間が経過してしまうとお米が乾燥して割れやすくなってしまいます。
水気を切る際は、ザルに上げて10回程度上下させてください。

- 炊飯器をセットする
- 炊飯器にお米、水を入れてスイッチをオンに。
あとは美味しいご飯が炊きあがるのを待ちましょう!